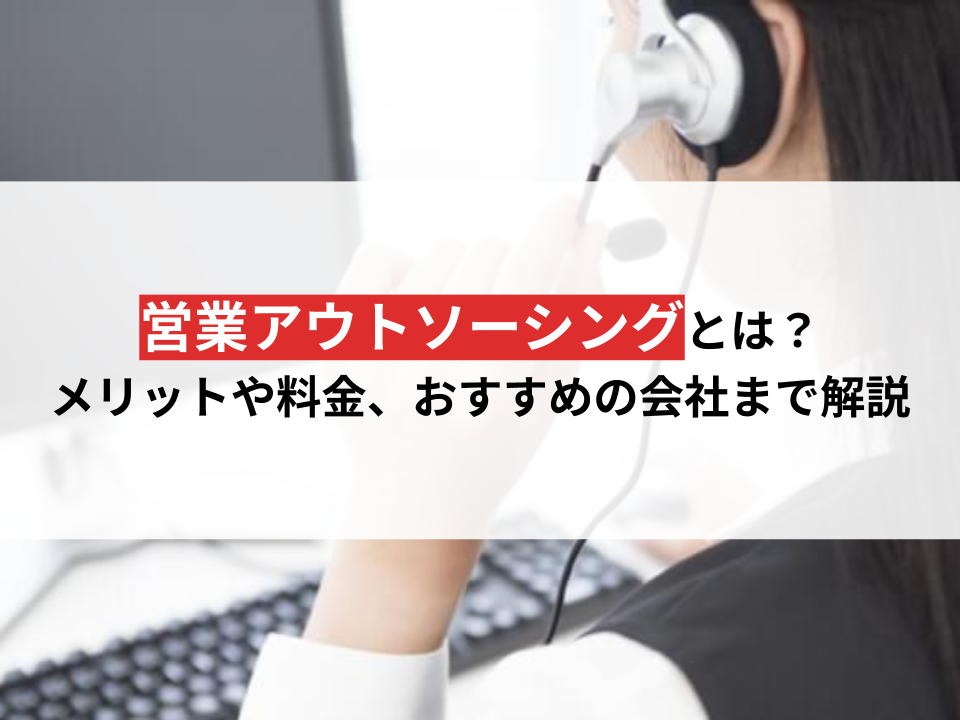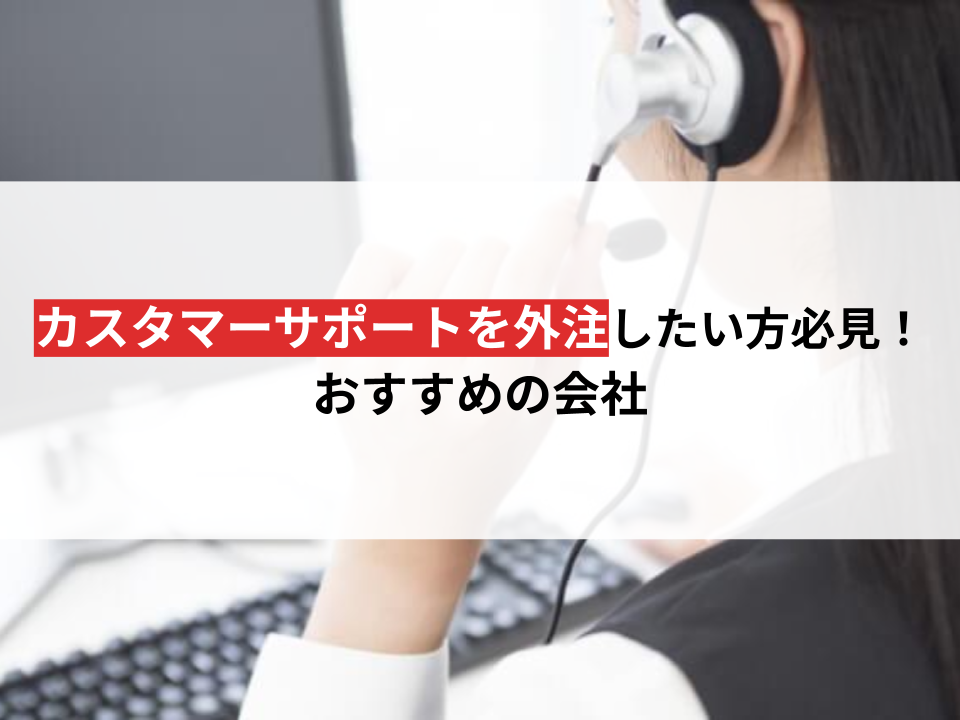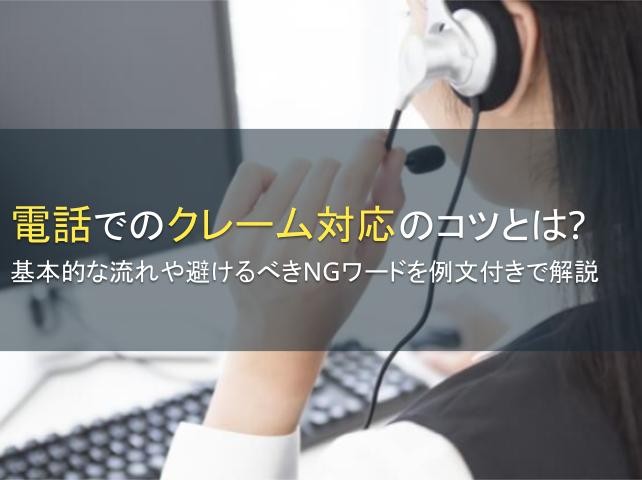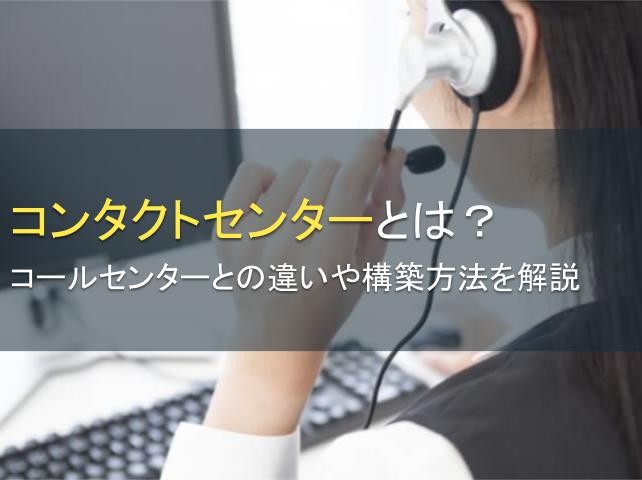コールセンターサービスの見積比較、特徴や費用相場を知って依頼・相談を|PRONIアイミツ

コールセンターサービス
あなたの希望に合ったコールセンターサービスが最短翌日までに見つかる
※2023年9月期_指定領域における市場調査
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
お急ぎの方はこちら
0120-917-819
(平日 10:00~19:00)
 初めてコールセンターを発注する方へ
コールセンター発注ガイド
初めてコールセンターを発注する方へ
コールセンター発注ガイド
コールセンターを発注する前に手順や費用・相場、発注のコツなどのポイントをおさえましょう!

コールセンターに関する新着記事
コールセンターに関する新着記事を紹介します。
おすすめのコールセンターサービス
PRONIアイミツおすすめのコールセンターサービスを東京・大阪といった地域、医療・不動産等の業界などに分けて紹介しています。
コールセンターの費用・相場
コールセンターに関わる業務の一般的な費用・相場情報について紹介します。
コールセンターのノウハウ
コールセンターに関する情報や発注ノウハウなどを紹介します。
コールセンターの実績事例一覧
コールセンターの実績事例を様々な条件で探すことができます。
- 大規模企業
- 24時間対応
- アウトバウンド業務
- 費用〜10万円
- 成果報酬型
- テレアポ代行
- スポーツ業界
- 録音機能
- 中規模企業
- 土曜日対応
- 費用11万円~30万円
- 小規模企業
- 秘書代行
- コールバック機能
- チャットサポート
- 顧客満足度調査
- 費用31万円~50万円
- 365日対応
- コンサルティング
- 祝日対応
- 費用51万円~100万円
- IT業界
- クレーム対応
- 日曜日対応
- 注文受付代行
- 費用101万円~300万円
- 費用301万円~600万円
- 年末年始対応
- インバウンド業務
- 費用601万円~1000万円
- 緊急時対応代行
- 費用1001万円〜
- EC・通販受注センター
- 費用公開なし
- カスタマーサポート代行
- マニュアル作成
- 電話受付代行
- 問い合わせ対応代行
- 申込受付代行
- 電話番号貸し出し
- 流通業界
- 運送業界
- 製造業
- 教育業界
- 銀行業界
- 食品業界
- 官公庁
- 自動車業界
- 商社業界
- イベント業界
- 福祉業界
- 美容業界
- 飲料業界
- Webサービス業界
- 生活用品業界
- アパレル業界
- 電子機器業界
- 小売業界
- 建設業界
- ホテル業界
- 旅館
- 金融業界
- サービス業界
- スーパー業界
- 宝石業界
- コンサルタント業界
- エネルギー業界
- 通信業界
コールセンターのよくある質問
コールセンターについてのよくある質問を集めてみました。業者を決定するまでには、自社の業態や依頼内容に応じたさまざまな疑問点が浮かぶものです。発注後のお客様へのヒアリングを行っているぜひアイミツでは、細かな疑問点もしっかり把握しています。
- インバウンドのコールセンターはどのような業種で利用されていますか?
- A 一般的な業種を幅広くカバー、多くの業種で利用されている。
- 電化製品メーカー、通販事業者、保険、インターネット接続業者、食品メーカー、銀行など、様々な業種で利用されています。用途は、カスタマーサポート、キャンペーンの問い合せ対応、商品やサービスの購入・予約、クレーム対応、秘書サービス等に多く利用されています。期間は数日〜年単位まで、要望に応じて利用可能です。
- 土日や祝日も対応してもらえますか?
- A 必要な曜日・時間帯など細かく設定した使い方も可能!
- 多くのコールセンター事業者は、24時間365日対応可能です。必要な曜日・時間帯など細かく設定できますので、むだなく必要なときだけご利用できます。ただし、電話先とのトラブルの発生などに備え、発注側企業でも夜間や休日に待機しなければならないこともありますので事前にご調整ください。
- 契約期間はどれぐらいから発注することはできますか?
- A 長期的な発注から1日単位での発注まで柔軟な依頼の仕方が可能。
- 1日から発注できるコールセンター事業者が多数あります。短期間や緊急の場合でも、電話先とのトラブルにつながらないよう、トークスクリプトやマニュアルを充分に整備しましょう。また、契約期間に関わらず、システムの設定やスタッフ教育などの初期費用がかかりますので、見積もり請求時にお問い合わせください。
- 個人情報の管理はどのようにされていますか?
- A 情報の管理には慎重な対応をしているが、事前に確認しておくことは大事。
- プライバシーマークの取得や、個人情報保護方針を独自定めるなど、各コールセンター事業者で個人情報の保護につとめています。発注をおこなう前に、あらかじめセキュリティ設備や個人情報の管理方法、万が一漏洩した場合の対処方法、また、スタッフの教育について充分にご確認ください。
- コールセンター委託の他に依頼できることはありますか?
- A マニュアルやトークスクリプトの作成なども依頼することも可能。
- コールセンター業務に付随する、マニュアルやトークスクリプトの作成を依頼することができます。また、小規模企業や個人事業主の方の利用が多い電話秘書やバーチャルオフィスサービス、サンクスレター等書類の送付、コールセンター機能を発注側企業内に構築するサポートをおこなっているコールセンター事業者もあります。
- オペレーターはどのような研修を受けていますか?
- A 一般的なマナー教育だけでなく、情報セキュリティなどの研修を受けている場合も。
- 良質なコールセンター運営業者では、電話先に対するマナーはもちろん、情報セキュリティや担当する業界についての研修をオペレーターに対しておこなっています。オペレーターの対応が企業イメージや顧客満足度に影響を与えますので、見積もり請求時には、オペレーターの研修内容や定着率などをもとにオペレーターの質を充分にご確認ください。
- コールセンター利用にかかる費用を教えてください。
- A 初期費用プラス利用料金、が費用としてかかってくる。
- まず、システムやトークスクリプトの設定、スタッフ教育などの初期費用がかかります。毎月の費用は、基本料金+利用した分、または固定の金額がかかります。なお、月額固定の場合は、設定された件数を超えると超過料金が請求されます。業者によっては、初期費用の中にマニュアルやトークスクリプトの作成が含まれていない場合があるので見積もり請求時にご確認ください。
- 通信販売やキャンペーン問い合せを発注した場合、商品や景品の発送もお願いできますか?
- A 物流関係と提携しているケースなどは依頼することも可能。
- 一部のコールセンター事業者で可能です。コールセンター事業者には、物流や発送代行、貸し倉庫サービスをおこなっているグループ企業や提携企業があるので、発送代行まで委託したい場合はそのような業者に発注しましょう。また、発送代行業者全体で宅配会社と契約しているため、個別で発送するより宅配コストが抑えられるメリットが発生するでしょう。
- コールセンター業務に関する一部の業務のみの発注も可能ですか?
- A 幅広く依頼することも、一部を依頼することもどちらも可能。
- 一般的に可能です。コールセンターの構築、オペレーターの教育・管理、トークスクリプト・マニュアルの作成それぞれ個別に発注することができます。また、各コールセンター事業者で取り扱っている、物流代行やDM発送代行など、コールセンター以外のサービスも単体で発注可能な場合が多いでしょう。
- 見積もりの際は何を用意する必要がありますか?
- A 予算や期間はもちろん、目標値なども相談することが費用対効果を高める。
- 発注したい期間や予算に加えて、細かい条件を揃えるより前に、どのような業務を委託し、どのような目標を達成したいのかを発注側企業で検討をおこなうことをおすすめします。コールセンター事業者はその情報に基づいて座席数や運営時間などのプランの提示や効率的な運用方法などのコンサルティングをおこなってくれるでしょう。